
大藪大麻裁判に続き、もう一つ大麻取締法違反の無罪が争われている裁判がある。2025年3月11日、さいたま地方裁判所熊谷支部401号法廷にて、第2回公判(裁判長:菱田泰信)が開かれた。今回は、検察側の立証として、本件大麻の鑑定を行った神奈川県警察科学捜査研究所(以下、科捜研)の技術職員(以下、鑑定人)に対する証人尋問が行われた。
今回の法廷では、大麻事件における鑑定の一端が明らかにされ、注目すべき裁判と思われた。また、大藪大麻裁判の控訴審の際には、傍聴者に対する身体検査が行われるなど、厳しい警備体制が敷かれていた。他方で今回は、そのような様子は全くみられなかった。裁判所の対応に、地域差がうかがえる。
本件の経緯と概要
被告人の柴﨑和哉さんは、2024年2月29日に「みだりに」大麻を所持した(大麻取締法24条の2第1項違反)として、同年7月10日に在宅で起訴された。大麻取締法改正以前の事件である。問題となった物は、「大麻である緑褐色葉片合計約4.255グラム及び大麻を含有する緑褐色葉片等約0.41グラム」であった。
当初、管轄裁判所は、さいたま地方裁判所秩父支部であった。しかし、同年10月21日、さいたま地方裁判所熊谷支部から、合議で審議する旨の通知があり、担当が同支部へと移行した。
公訴事実について、主任弁護人の丸井英弘弁護士は、次のように主張している。本件大麻所持は「国民の保健衛生の保護」を侵害する可能性がないのであるから、「みだりに」の部分を認めない。そして、本件葉片が大麻取締法上の「大麻」であるかについては、争う姿勢である。
また、再鑑定により、本件葉片のうち種子を除外した量(大麻取締法上の「大麻」に種子は含まれない)および(種子を除いた)本件葉片が心身にもたらす具体的な効果を明らかにすること、すなわち大麻草の有害性立証を求めた。
柴﨑さんは、2024年12月24日に行われた第1回公判の冒頭意見陳述で、次のように述べた。「少量の大麻を個人の休息の場で使用」しており、それにより自身の「日常生活に支障や弊害といったものはなかったし、社会に対する弊害もなかったと考えている」。そのうえで、「私が懲役刑を受けるほどの重罪を犯したというのであれば、私が大麻取締法の保護法益とされる『国民の保健衛生の保護』や『社会の安定の維持の保護』を、どれだけ、どのように侵害したのか」を具体的に示してほしいという。
さらに、「アルコールがまったく体に合わないので、社会生活で疲れた心身をリラックスしたいときにお酒で酔うのと同じように、私は大麻で酔うことでリラックスし、充実した気分は睡眠の質の向上に繋がっていた」という自身の経験をふまえ、「『酔うこと』は原則として自由である」との主張を行った。
大麻鑑定では何が行われるのか
本件は、次の項で述べるように、鑑定の妥当性が争点となった。第2回公判での弁護側・検察側のやり取りをみる前に、一般的な大麻鑑定の流れを以下に示しておく。基本的な手順は、資料の重量を計測したのち、形態学的検査と成分分析が行われる。
形態学的検査とは、剛毛がみられるかどうか、顕微鏡で確認する検査である。大麻の剛毛は独特の形をしており、加工されて植物の原型を保っていなくても必ず残っているとされる。
成分分析では、鑑定資料中のTHC(テトラヒドロカンナビノール)の有無が確認される。分析方法は、薄層クロマトグラフィー、ガスクロマトグラフィー質量分析などである。
分析結果を評価する際には、鑑定対象の資料と、あらかじめTHCであると確認されている標準品を含む資料を、同じ条件で同時に試験し、結果を比較対照する必要がある。結果が同じであれば、分析対象の資料は「大麻である」と評価される。
なお、鑑定結果が「大麻を含有する」と記されることがある。「大麻である」という表現は資料のほぼ全体が「大麻」であることを意味するのに対し、「大麻を含有する」は「大麻」でない物の混合があることを意味する。
本件葉片は「大麻」といえるのか
本件の第2回公判では、検察官の証人尋問により、鑑定人がどのように鑑定を行ったかが明らかになった。鑑定された物は3点のチャック付きビニール袋に入った葉片。鑑定の内容は、①本件葉片は大麻か否か、②葉片の重量の2点であった。
①については前項で述べたとおり、形態学的検査と成分分析によって、本件葉片は「大麻である」あるいは「大麻を含有する」緑褐色葉片である、と判断したようだ。鑑定人によれば、本件葉片には大麻に特徴的な外部形態である剛毛が認められた。薄層クロマトグラフィーでは標準品のTHCと一致する結果がみられ、ガスクロマトグラフィーでも、THCが検出されたという。また、呈色反応検査でも大麻特有の反応(紫紅色)を示したとのことであった。
②は、てんびんを用いた計量の結果、「大麻である緑褐色葉片」が約4.255グラムと、「大麻を含有する緑褐色葉片等」が約0.41グラムであったという。「大麻を含有する」とした理由についても前項のとおり、本件葉片に種子のようなものが混在していたから、とのことであった。
これに対して、丸井弁護士は、厚生省薬務局麻薬課『大麻(CANNABIS)』(1976年)を提示し、大麻に似た剛毛を持つ植物があるという情報を知っているかと尋ねた。これに対し、鑑定人は、知らないと述べた。
次に、問題となる葉片が大麻であるかどうか判断する際の、基準となる標本は存在するかどうかを尋ねた。これについては、標本はないが科捜研にて参照することとなっている写真などが標本になる、との回答がなされた。
また、本件葉片からTHCが検出されたと判断する際の標準品が、大麻草由来か化学合成由来かを確認したかどうか尋ねると、それはしていないという。本件は法改正前の事件であり、葉片から検出されたTHCが大麻草由来か化学合成由来かによって法定刑の上限が変わるため、重要な事項である。
弁護側は、先述の『大麻(CANNABIS)』や大麻規制のあり方についての論文等と、大麻草の歴史やその精神作用などに詳しい2人の証人を証拠調べ請求していた。しかし、検察官はいずれも不同意あるいは必要性なしとし、裁判官も請求却下の判断を下した。あらかじめ申立てをしていた再鑑定については、鑑定人は可能であると回答したものの却下となった。
次回は、さいたま地裁熊谷支部5月13日13時30分より行われる。弁護側請求証拠がすべて却下されたため、被告人質問で柴﨑さん自身が、弁護側請求証拠のなかで主張する予定であった事項も含めて発言することになった。
最後に、柴﨑さんが意見陳述で「大麻草を個人使用のために少量所持することに対して刑事罰を科すほどの大麻草に有害性があるのか、その科学的根拠を明らかにしていただきたい」と強調して、第2回公判は終了した。
401号法廷前での報告会
閉廷後、柴﨑さんらは今日の審理についてコメントした。
丸井弁護士は、「他の植物にも似た剛毛があることを確認していない、標本もない、との証言が得られたのは大きかった」と振り返った。
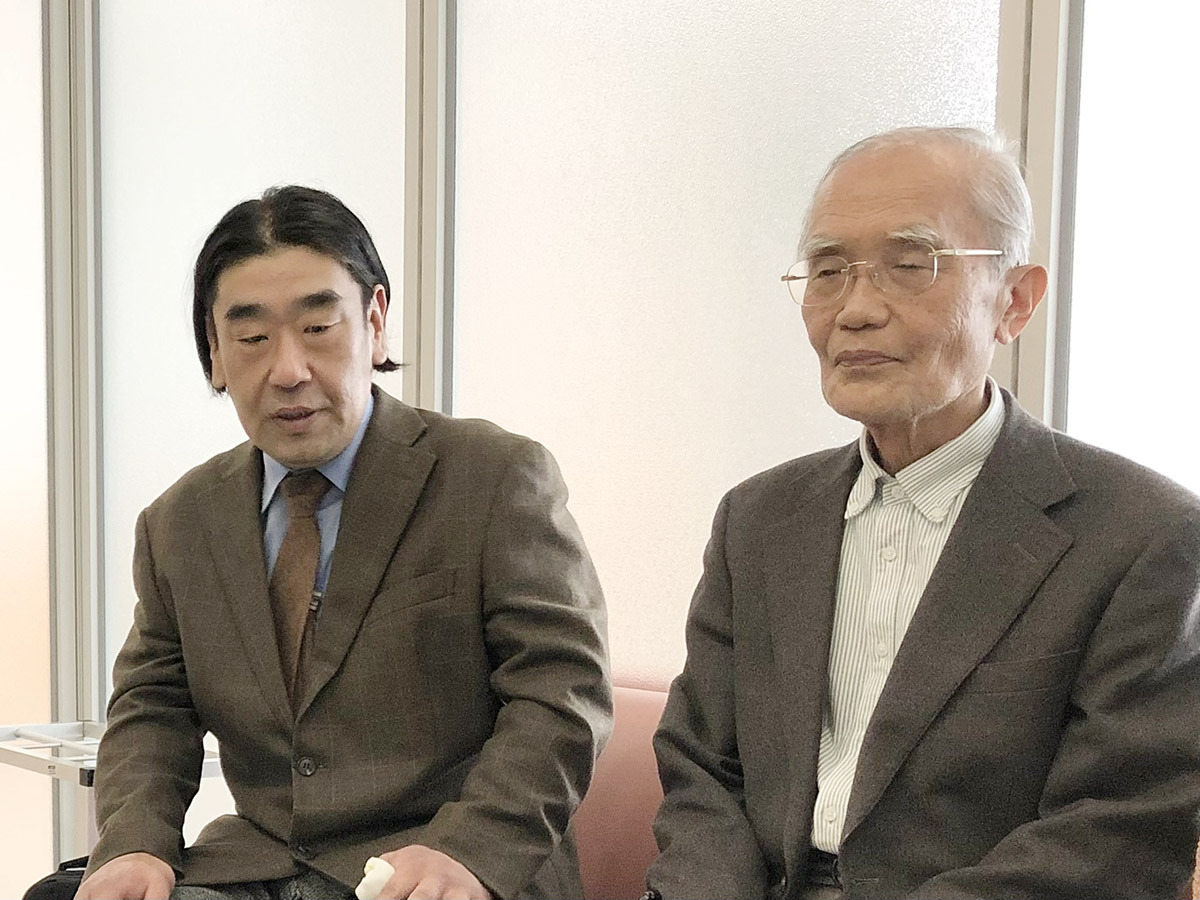
しかし、弁護側の請求証拠がすべて却下されたことをふまえて、「(大麻の有害性を認めた判例は40年前であるのに)裁判官には有害性を改めて証明しようとする姿勢がみられず、判断能力が機能していない」と指摘した。少数者の権利の保護を役割の一つとする司法には、「酔うこと」の自由に向き合うことも期待したいところである。
また、「せっかく合議制になったのに、陪席の裁判官らはほとんど発言せず、合議の意味がない」と審理の体制にも言及した。この点は、大麻事件にとどまらず刑事事件全体に関わる問題であろう。
さらに、今後の公判の行方については、「被告人自身が全ての主張を行わなければならなくなったが、柴﨑さんの『講演会』(次回行う予定の2時間の被告人質問)で国民的うねりを起こしていきたい」と語った。これに対して、柴﨑さんは「今回は期待はずれなところもあったが、次回の5月13日には、自分の思いを伝えたい」と締めくくった。
法改正に至るまで、大麻使用の処罰にはさまざまな問題が指摘されてきた。改正法が施行されたからといって、その問題がなくなったわけではない。本件の争点となった大麻鑑定(そもそも葉片は「大麻」といえるのか)の妥当性も、大麻がいかに「国民の保健衛生」を侵害するかという議論の前段階に位置づけることができよう。大麻の所持や使用の処罰に潜むさまざまな問題を、引き続き明らかにしていきたい。
なお、大麻の有害性を認めた判例は、最一小判昭60・9・10判時1165号183頁(LEX/DB27803849)、最一小判昭60・9・27集刑240号351頁(LEX/DB25352393)がある。薬物一般および大麻の鑑定については、小森榮『もう一歩踏み込んだ薬物事件の弁護術』(現代人文社、2012年)に詳しい。本稿もこれを参照している。また、大麻政策については石塚伸一ほか編著『大麻使用は犯罪か?——大麻政策とダイバーシティ』(現代人文社、2022年)に詳しい。
(お)
(2025年04月08日公開)

