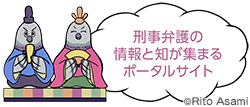東京電力福島第1原子力発電所で2011年に起きた事故をめぐり、業務上過失致死傷罪に問われて強制起訴された、ともに同社元副社長で原子力部門トップを務めた武黒一郎被告(78歳)と武藤栄被告(74歳)に対し、最高裁判所第2小法廷(岡村和美裁判長)は3月5日、1、2審の無罪判決を支持する決定をした。
2人が、同原発に敷地を超える高さ10m以上の津波が襲来するという「現実的な可能性を認識していたとは認められない」とした1、2審の判断を踏襲し、検察官役の指定弁護士の上告を棄却した。2人の無罪が確定した。
一緒に強制起訴された同社元会長の勝俣恒久氏(1、2審は無罪)は昨年10月に84歳で死亡して公訴棄却となっており、未曾有の原発事故に関する刑事責任は誰も負わない結果になった。
業務上過失致死傷罪に問い禁錮5年を求刑
3人は、同原発で津波に起因する事故が起きないよう防護措置を取る業務上の注意義務があったのに怠り、漫然と原発の運転を続けた過失により、2011年3月11日の東日本大震災で津波を受けて原子炉建屋に水素ガス爆発を発生させたため、近くの病院の入院患者ら44人に長時間の搬送を伴う避難を強いて死亡させた、などとして業務上過失致死傷罪に問われた。
原発事故で被災した福島県民らが2012年に刑事告訴。検察は不起訴にしたものの、検察審査会の「起訴議決」を受けて、指定弁護士が2016年に3人を強制起訴した。3人に対し、いずれも禁錮5年を求刑していた。
15.7mの津波試算への評価が審理のテーマ
3人が同原発に巨大な津波が襲来する可能性があることを事前に認識できたか(予見可能性)が最大の争点だった。政府の地震調査研究推進本部(地震本部)が2002年に「福島県沖を含む日本海溝でマグニチュード(M)8.2級の津波地震が30年以内に20%程度の確率で起きる」との地震予測(長期評価)を公表したこと、さらに、これに基づき東電が2008年に同原発に高さ15.7mの津波が襲来する可能性があるとの試算を得ていたことへの評価が審理のテーマになった。
2審・東京高裁の無罪判決(2023年1月)は、長期評価について「10mを超える津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような情報だったとは認められない」と信頼性を否定し、原発の運転停止を前提に「ただちに対策を義務づけられるような具体性や根拠」を伴うものではなかったと判断した。15.7mの津波の試算についても「現実的な可能性を認識させるような数値であったとは認められない」と結論づけていた。
指定弁護士は最高裁への上告趣意書で、高裁判決が予見可能性の判断にあたって「現実的な可能性」の認識を求めたことに対し「これまでの『具体的な可能性』よりも相当に程度の高い可能性を要求している」と批判。それを踏まえて「長期評価は高さ10mを超える津波が襲来することの具体的可能性を認識させる性質を備えた情報だった」と反論していた。
最高裁も長期評価に否定的な材料を列挙
最高裁は今回の決定で長期評価について「三陸沖北部から房総沖までの海溝寄りを1つの領域として、M8.2前後の規模の津波地震がどこでも発生するとした点は、一般に受け入れられるような積極的な裏づけが示されていたわけではない」と見立てた。地震本部が公表翌年の2003年に発生領域・確率の評価の信頼度を「C」(やや低い)としていたことを念頭に「地震本部による信頼度の評価も低かった」と指摘。さらに「原子力安全にかかわる行政機関、防災対策にかかわる地方公共団体も全面的には採り入れていなかったとみられる」と否定的な材料を並べた。
そして「長期評価の見解は同原発に10m超の津波が襲来するという現実的な可能性を認識させるような性質を備えた情報だったとまでは認められない」と言い切った。「被告はそうした現実的な可能性を認識していたとは認められない」と予見可能性を否定して無罪を言い渡した高裁の判断を支持し、指定弁護士の上告を棄却した。
補足意見は津波試算の報告遅れを問題視
対策を取っていれば事故は避けられたか(結果回避可能性)も争点だった。高裁判決は東日本大震災が観測史上最大だったことなどを理由に、防潮堤や防潮壁の設置、重要機器の水密化といった浸水防止策を導入していても「本件事故を回避可能だったと認めるに足りる証拠はない」と否定していた。指定弁護士は上告趣意書で、運転停止をせずともこれら「すべての対策を講じていれば全電源喪失に至ることはなく事故を回避できた」と主張したが、最高裁は見解を示さなかった。
第2小法廷の4人の裁判官のうち検察官出身の三浦守裁判官は審理に加わらず、他の3人の裁判官全員一致の意見だった。三浦裁判官は原発事故をめぐる国賠訴訟の最高裁判決(2022年6月)で、津波襲来の予見可能性を肯定したうえで国の賠償責任を認める反対意見を述べていた。
今回の決定では草野耕一裁判官が補足意見を記し、東電が15.7mの津波試算をすぐに国に報告しなかったことを問題視。「被告らが報告義務を速やかに履行していたとすれば、国は東電に津波に対する防護措置を講じるよう命令し、原子炉はすべて運転を停止するに至り、全電源を喪失しても本件結果を回避できた可能性があったのではないか」との見解を示した。ちなみに、東電が試算結果を国に報告したのは約3年後、地震発生の4日前だった。
指定弁護士「最高裁の見解が支離滅裂」
指定弁護士は3月6日に東京都内で記者会見した。
石田省三郎弁護士は、同じ第2小法廷の2022年6月の判決が15.7mの津波試算について「安全性に十分配慮して余裕を持たせ、当時考えられる最悪の事態に対応したものとして、合理性を有する試算だった」と評価したくだりを読み上げ、今回の決定に対し「矛盾している。最高裁の見解が支離滅裂になっているのでは、と率直な感想を持つ」と語った。
さらに「国の機関である地震本部の見解を軽視し、現在の原子力行政におもねった不当な判断として、厳しく批判されなければならない」と力を込め、「検察審査会の議決や民意を生かせなかったことは、指定弁護士として残念でならない」と総括した。
「次の原発事故を引き起こす可能性がある」
裁判の起点となる刑事告訴をした「福島原発告訴団」も都内で記者会見をした。告訴団と刑事訴訟支援団は、3月21日に定年退官する草野裁判官が以前に東電と関係が深い法律事務所を共同経営していたとして審理から外れるよう求め続けており、3月3日にも最高裁へ要請したばかりだった。
原発事故で被災した武藤類子・告訴団長は「最高裁の正義にいちるの望みをかけてきた。(原発事故が起きた)3月11日の直前にこのような判断を出され、事故の被害者を踏みにじる冷酷さを感じる。事故を起こした企業の経営者の責任を問わないことで次の原発事故を引き起こす可能性があると、裁判所が理解してくれなかったことが何より悔しくて残念。全く納得していない」と時折声を詰まらせながら話した。
告訴団の弁護団代表で、刑事裁判の被害者参加代理人を務めた河合弘之弁護士は「国家機関の地震本部で最高レベルの地震・津波学者が徹底討論して出した(長期評価という)結論を軽視して、何に依拠して地震・津波対策をすれば良いのか」と決定を非難。海渡雄一弁護士も、予見可能性の判断にあたって「地震発生の現実的可能性という規範を立てられると、いかなる対策も無効になる。次の原発事故が避けられない」と語気を強めた。
福島原発事故をめぐっては、脱原発を訴える東電の株主が旧経営陣を相手取って事故による損害を個人の財産で同社に賠償するよう求める株主代表訴訟を起こし、1審・東京地裁は2022年7月に勝俣氏、武黒氏、武藤氏と清水正孝・元社長の4人に13兆3,210億円の賠償を命じている。2審・東京高裁は6月6日に判決の予定だ。
株主代表訴訟の株主側代理人でもある海渡弁護士は「今回の決定の論理はあまりにも粗く、2022年の最高裁判例とも矛盾している。根本的に間違っているので影響はない」との見方を示した。
◎著者プロフィール
小石勝朗(こいし・かつろう)
朝日新聞などの記者として24年間、各地で勤務した後、2011年からフリーライター。冤罪、憲法、原発、地域発電、子育て支援、地方自治などの社会問題を中心に幅広く取材し、雑誌やウェブに執筆している 。主な著作に『袴田事件 これでも死刑なのか』(現代人文社、2018年)、『地域エネルギー発電所──事業化の最前線』(共著、現代人文社、2013年)などがある。
【編集部からのお知らせ】
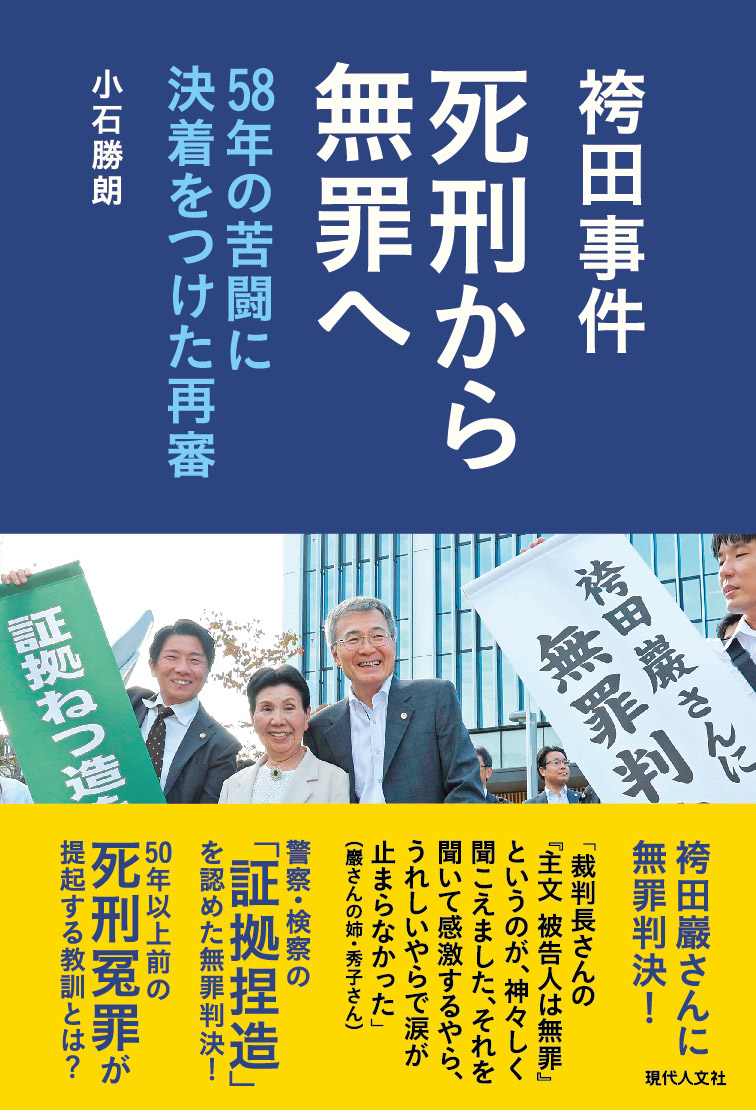
本サイトで連載している小石勝朗さんが、2024年10月20日に、『袴田事件 死刑から無罪へ——58年の苦闘に決着をつけた再審』(現代人文社)を出版した。9月26日の再審無罪判決まで審理を丁寧に追って、袴田再審の争点と結論が完全収録されている。
(2025年03月21日公開)