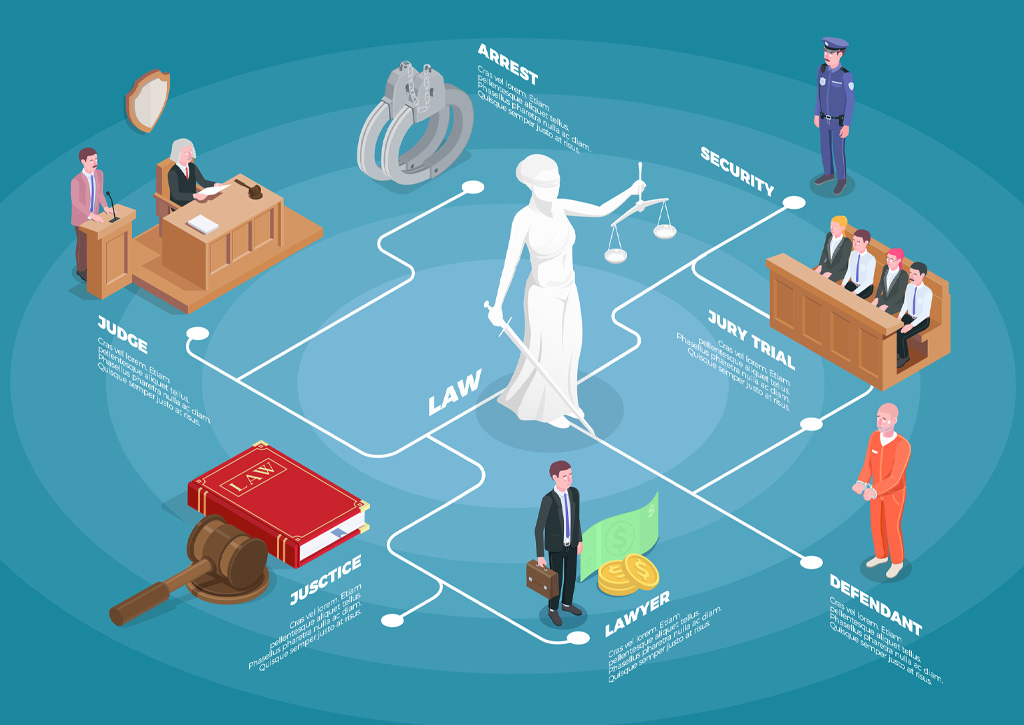
⑶ 「確定した裁判の執行を確保するための方策」についての議論
部会の第2回会議では、所在不明のために刑の執行のための収容ができなかった者を「とん刑者」と呼び、近時の事例が紹介されている[1]。これに対応するために、たたき台で提案されているのが、3−1「捜査段階における強制処分同様の調査権限を、刑の執行段階についても整備すること」、3−2「実刑判決が確定した者が収容を免れるために逃亡する行為に対する新たな罰則を設けること」、3−3「刑が確定した者が国外にいる間,刑の時効の進行を停止するものとすること」、3−4「罰金の裁判の告知を受けた者が出国することにより労役場留置の執行を免れることを防止する仕組みを設けること」の4項目である。
3−1は逃亡者の所在確認や追跡のための資料獲得のための強制処分を創設する提案である。認めるべき処分の範囲については意見が出されている[2]ものの、制度の創設自体には異論は出されていない。裁判官の発する令状によること、処分に対する不服申立ても認めるとされていることから、濫用のおそれは小さいと考えられたからであろう。
3−2は、刑の執行(収容)のための呼び出しを受けた者が正当な理由なく出頭しないことを犯罪とする、という提案である。これに対しては明確な反対意見[3]がある。この反対意見の前提には、罰則を設けずとも、刑訴法の刑の執行手続に従い、執行のための呼び出しをかけ、呼び出しに応じないときは収容状を発するという刑訴法484条の手続が適切に行われれば足りるとの認識がある。勾引状と同一の効力がある収容状(刑訴法488条)による直接強制が可能であるのに、罰則を設けて出頭を確保しようとすることは、過剰な罰則だといえるからである。
3−3の国外にいる間の刑の時効を停止するというも提案には、反対意見は出されておらず、検討課題に挙げられている、罰金、科料、没収について刑の時効の進行を停止させるべきか、という点について議論があった程度である。
3−4は、第1回会議で労役場留置の執行を確保する手段が必要であるとの意見が出されていた[4]ことに対応する提案である。自由刑については国外に逃亡することが事実上刑の執行を免れることにつながるのに対し、罰金等については、刑の言い渡しを受けた者が国外にいても執行が可能である。そこで、「罰金を完納することができないおそれ」を要件として身体拘束を認める制度を創設しようというのである。ここでも刑(換刑処分としての労役場留置)の執行確保のための勾留と、労役場留置が可能になる30日の期間(刑法18条5項)の前に出国することを防ぐ身体拘束制度の提案がある。
以上の3−1〜3−4の提案では、あくまで刑の執行を逃れることを許さない制度が考えられている。部会ではこの提案に対して反対意見は出されていない。しかしもともと、刑の執行ができない場合を想定するからこそ、刑の時効の制度が存在する。国外逃亡のケースでは、国外にいる期間は刑の時効を停止するという3−3の提案は同様の停止期間を定める公訴時効の場合(刑訴法255条1項)と同じであり、合理性があるのかもしれない。しかし、刑の執行確保のために勾留を利用することや新たな身体拘束制度を創設することまで必要なのか、疑問を感じる。
5 おわりに
連載第1回で指摘したように、立法事実である逃亡事案の中には、身柄の確保に失敗したケースが含まれている。逃走は、被告人、刑が確定した者の側にだけ原因があるとはいえない。たたき台に示された権利制限の強化や罰則による抑止を考える前に、保釈や執行停止の際の条件設定を精緻化するとか、検察庁の収容手続を見直すことなどによって、逃走を防ぐ方策をまず考え、現行制度によっては対応できない場合に限って新たな制度を導入するべきである。このような考え方は、すでに少数ながら部会の中で出されている。これらが今後部会において共有され、被告人等の権利保障と両立し得る制度に向けて議論が深められていくことを期待したい。
◎執筆者プロフィール
水谷規男(みずたに・のりお)
1962年三重県生まれ。1984年大阪大学法学部卒業。1989年一橋大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。三重短期大学、愛知学院大学を経て、現在、大阪大学大学院高等司法研究科教授。専門=刑事法。主な著作に、『未決拘禁とその代替処分』(日本評論社、2017年)などがある。
注/用語解説 [ + ]
(2021年06月02日公開)

