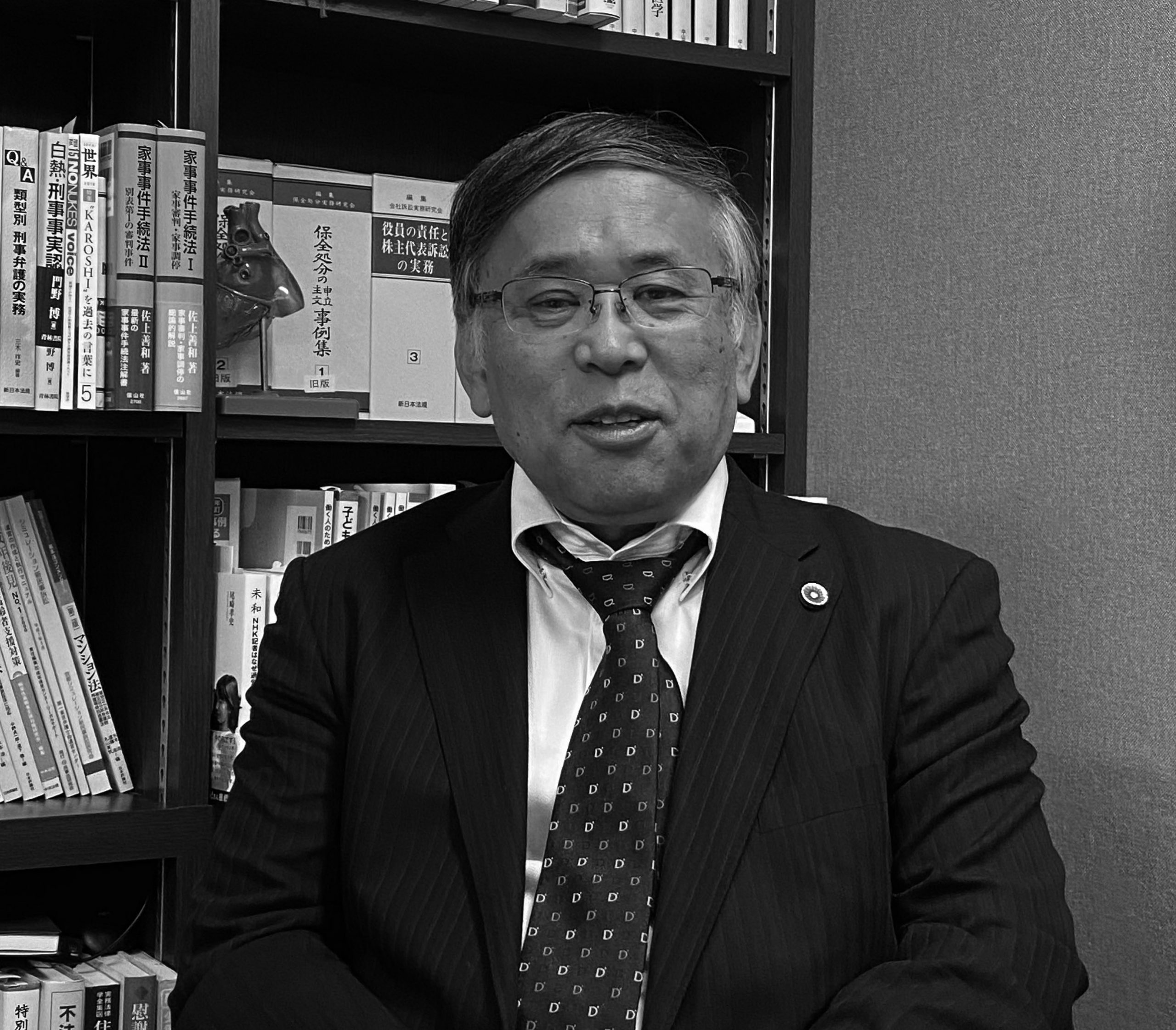1 前近代的な捜査に挑む
村山 野平先生はこれまでに数多くの刑事事件を担当されていますが、その中でもまず、2003(平成15)年に起きた鹿児島県議会議員選挙に絡んで、公職選挙法違反(買収)の被疑事実で13名が起訴され、後に全員が無罪になる志布志事件についておうかがいしたいと思います。先生が弁護人としてついた方と初めて会ったときどんな印象を受けましたか。
野平 私が弁護人としてついた永山トメ子さんは、当時72歳でしたが、すごく毅然とした方でした。「そんなお金もらってもいない」「会合に参加したことはない」「自分が嘘の話をすれば、周りの人に迷惑が掛かる。だから、やっていないものはやっていないとしか言いようがない」とキッパリとおっしゃっていました。毎日、刑事から責められ、「やったと言えば楽になる」と言われ続けたにもかかわらず。弁護士になって5年目の頃でしたが、この人はもらっていないと強く感じました。
村山 志布志事件における捜査機関の取調べはとても過酷なものだったと聞いています。
野平 親族の名前を書いた紙を踏ませて自白を強要した“踏み字”、取調室で「自分がやりました」と大声で叫ばせる“叫ばせ”という前時代的な取調べがありました。取調べは本当に過酷で倒れる人がいたくらいです。永山トメ子さんも任意捜査の段階で取調べられて、自宅に帰ってから倒れて救急車で運ばれています。一番驚いたのは、弁護権の侵害です。弁護士が接見から帰ると被疑者を必ず取調室に呼んで、弁護人とのやりとりを聞き出す。こういうことが続くと被疑者は、弁護士と会うことが嫌になるわけですね。だから、一生懸命弁護をしようとしても、「弁護人が来るから自分は苦しい立場になるんだ」と思い込んで弁護人を解任するケースが、志布志事件では何件も起こっています。
村山 このような状況下での接見は大変に気をつかうものだったのではないでしょうか。
野平 長い間勾留されていると、拘禁反応が出て、精神的に非常に動揺しやすくなります。だから、虚偽自白をしないようにするために交代制で接見に行って、一息つかせてあげる。震えが出たり、言語機能に障害が出たり、冷や汗が急に出たりと、永山さんには自律神経失調症の症状が出ていました。そういう状況でしたが、僕らに会うと安心して、「帰り道、気をつけてくださいね」と僕らのことを心配してくれるような人でした。鹿児島市内から往復で4時間かかるので。繰返しの接見により弁護人との信頼関係ができ、永山さんに僕らを気づかうほどの心の余裕ができたことは、否認を続けるための一助になったのかなとは思いますね。
村山 先ほど、弁護人の解任の話をされましたが、ほかにも弁護権の侵害はありましたか。
野平 懲戒請求と解任請求を検察官が行うと予告をしてきました。第1回公判を開けばその場で解任請求すると。接見時に親族の書いた手紙をアクリル板越しに見せたことが接見禁止規定に違反するものであり懲戒理由に当たるということが理由です。そして、裁判官が我々に「今日の期日に関しては延期していいか」という相談をしてきました。当時、永山さんたち被告人全員には、公判終了時の24時まで、接見禁止決定があり、その第1回の公判期日に罪状認否まですると、公判廷自白をする者には保釈を認めなければならなくなったり、否認する者には、接見禁止の延長を求めるなどしなければならなくなる可能性があり、公判を維持できるほどの自白証拠が十分に集まっていなかった検察官は、なんとしても、公判を開かせたくなかったという思惑があったものと思います。第1回公判廷が開かれるということで、傍聴席は満室でした。私服の警察官が十数人入っていましたし、通常1人か多くても2人いる検察官は、被告人1人につき1人の検察官という感じで6人来ましたよ。普通はする挨拶もなく殺気立っていました。
村山 異様な雰囲気ですね……。
野平 本当に異様な雰囲気でした。しかも、裁判長が、「今日の公判は延期する」という趣旨のことを言われて、驚きの連続でした。その後、実際に裁判所が国選弁護人2名を解任するという出来事が起こりました。弁護士が、親族の手紙を見て「こういうふうに言っているよ」と言って示すことは接見禁止規定に違反するものではありません。僕らとしても、励ましの言葉であったりすれば、それは見てもらって、本人に家族の意向を伝えることは当たり前だと思います。それを違法行為として解任予告をして、さらには公判期日まで飛ばしてしまうという行為を弁護士会としてみすみす放置してしまっていいのかという意見が最終的には圧倒的になり、多くの議論を重ねた上で、弁護士会の全会一致という形で申入れをして、国選弁護人の推薦停止という結論に至りました。
村山 鹿児島県弁護士会による国選弁護人の推薦停止の決議は、国選弁護人制度、刑事弁護というものを毅然とした態度で弁護士みずからが死守したという意味で、重大な決断だったと思います。
野平 早期に裁判所と裁判官たちにも反省していただいて、二度とこういったことを繰り返さないという覚悟を持って臨んでいただきたいということで、被疑者・被告人の利益を守るベき立場から十分に警鐘を鳴らすことができたと思います。
村山 この志布志事件に対する警察や検察の対応について、どういう問題があったと思いますか。
野平 もう問題だらけです。自白を強要する捜査手法は論外ですが、検察官は、警察の指揮・指示をすることができるにもかかわらず、警察の言うことを鵜呑みにしてその方向性を誤ったのではないかと思います。検察官が警察をチェックしていく、起訴・不起訴を決める、証拠として足りないものがあればやらないように指示を出すといった仕組みを作らなければならない。これは警察の内部でも同じことが言える。買収事件は本部長指揮事件ですからね。県警本部長の指示系統が、通常はすごく働くそうですが、志布志事件ではなぜか働いてない。検察と警察にとって志布志事件は大きな汚点であり、こういうことを決して繰り返してほしくないです。
2 死刑求刑という重圧
村山 裁判員裁判の死刑求刑事件で初の無罪判決(2010〔平成22〕年12月10日。控訴審継続中に被告人死亡)が出た2009(平成21)年に鹿児島市で起きた高齢者夫婦の強盗殺人事件についておうかがいします。当時は裁判員裁判がスタートして間もない時期で、しかも強盗殺人事件という死刑求刑が予想された中での弁護だったと思いますが、弁護活動で工夫されたことはありますか。
野平 裁判員の気持ちをこちらの主張に向けていくかという点は、かなり意識しました。裁判員にぜひ現場を見てもらおうと考えました。「現場を知らずに判決はできない」「夜間の検証はさすがに難しいかもしれないが、昼間でもいいじゃないか」ということを強く訴えました。裁判官も、「現場は大事だ」ということで、裁判員を連れて行く決心をしてくれました。現場を裁判員たちに見せたというのは全国的に見ても珍しいのではないでしょうか。
村山 弁論ではどういった工夫をされましたか。
野平 裁判員に飽きられないように弁論は短くするという方針でした。これは新倉哲郎弁護士のアイデアです。プレゼンのやり方について、今はある程度、確立してきたのかもしれませんけど、当時は試行錯誤を重ねていた時期でした。裁判員が関心を持って、1時間集中して聞いてもらえる弁論をやろうということで、我々はホワイトボードに基本的・重要な用語を並べていって引きつけるという手法を採用しました。たとえば、スコップやDNA、網戸という用語ごとに分けて、合理的な疑いが残るものだと印象づけていきます。両面テープでホワイトボードにつけるタームを徹夜して作りました。
村山 弁論が終わった後、無罪への手応えはありましたか。
野平 検察官の論告求刑に関して、死刑求刑までやったわけですけど、裁判員の皆さんは聞いてない感じでした。それに対して、弁論は現場に行ったことが大きかったですね。「財布は残っていましたよね」「強盗がこんなことしますか」「金庫もまったく触っていなかったですよね」と現場で見ているわけです。裁判員たちが事実を認定していくうえで、「これはおかしい」「疑わしい」という話をおそらく協議の中でしていると僕らは思っています。だから、現場に行ったことと、それを印象づけるための疑わしさを耳に残る形でやりました。弁論が終わった瞬間、裁判員たちの顔色が変わったと思いました。手応えはありましたね。
村山 死刑を求刑されて無罪を勝ち取るということは、プレッシャーも相当あったと思います。この事件を担当されて、今、振り返って思うことはどういうことですか。
野平 僕は死刑廃止の立場です。無辜の者がもしかしたら死刑になるかもしれないという、刑事裁判の恐ろしさがあります。声を出さない人たちや声を出せない人たち、無実だと訴える力もない人たちもいるということを、我々は知らないといけないと思います。この事件では、無辜の者に対する死刑判決を回避できたということはよかったと思いますが依頼者の死の可能性という危険、まさに人の命をかけた弁護活動の危うさ、難しさを感じました。とくに、死刑求刑案件であるのに、これを防御する手段は、国選弁護人には、格別の配慮はなく、現場周辺を聞き込みしたり、開示証拠を手がかりに証人探しをするくらいのもので、近くにDNA型鑑定や指紋の専門家もおらず、自費で東京などの専門家に依頼するなどの過重な負担を負わされていると思います。裁判員もまた同じように非常に大きな負担を背負わされていると思います。
村山 この事件は検察官により控訴されましたが、控訴審でいかに原審の無罪判決を守るかという点についてはどのようにお考えでしたか。
野平 国選弁護人である我々としてはやれることは限られている。まして鹿児島は、控訴事件は宮崎(福岡高裁宮崎支部)に行かなければならないので、国選弁護人は任務終了になり、控訴審の弁護人は宮崎の弁護士が一からやるという話になる。それは名張事件のような事件を生む可能性があるわけです。一審の弁護人としても、控訴審で引き続きやったほうがいいのではないかと、控訴審の弁護態勢をどう構築するかということを盛んに議論しました。具体的には、僕たちは私選弁護人となり、宮崎県弁護士会の刑事弁護に熱心な方を募り、さらに、日弁連の有志にも声をかけ弁護体勢を整えました。また、一審の裁判員は「疑わしきは被告人の利益に」の原則を貫き、無罪という結論に達しました。ですので、検察官の有罪の証拠である網戸のDNA型鑑定の問題点をさらに徹底的に叩くことや遺留指紋の不自然性などをあきらかにするため、専門家の意見をまとめること、これを柱に無罪推定原則の貫徹を裁判所に求めることなどを盛んに議論しました。最終的には有志で多くの弁護士に参加していただいて16人の大弁護団になりました。
3 依頼者の「生きる」ということに寄り添う
村山 これまで個別具体的な事件のお話をうかがってきました。ほかにも多くの刑事事件をご経験されてきたわけですが、野平先生の刑事弁護についてのお考えをお聞かせください。
野平 多くの刑事事件が有罪案件です。有罪の人たちがどう更生していくのかに対して、弁護士はどこまで関われるのか。多くは裁判という場でしか関われない。僕が最も印象に残っている案件は、子ども2人を抱えた水商売の女性と同棲をしていた加害者です。朝5時くらいに起きて、遠くまで通って昼間の仕事をしている。同棲していた女性は、夜9時くらいから、夜の店に働きに出る。彼が仕事から帰ってきて女性が帰ってくるまでの間女の子の面倒を見ていました。女性が帰ってくるのが夜中の2時くらいなので、彼の睡眠時間はわずか3〜4時間しかないわけです。そういうストレスが溜まっている状況で、言うことを聞かずに泣き叫ぶ下の女の子を蹴飛ばして死なせてしまった。もちろん殺すつもりはなかった。執行猶予を求める弁論をしましたが3年半ぐらいの実刑判決を受けました。彼は刑務所から出てきてからもう十何年経つのですけど、出てきてから、女の子の父親と母親に対して、僕が窓口になって自分が働いたお金をずっと送り続けました。
村山 事件後も長い間その男性とおつきあいされてきたわけですね。
野平 刑事弁護は、生きるということがいかなることなのかについて考えさせられる。依頼者の生きるということに対して、我々がどういう形で関われるのかということが、弁護人としては一番重要なところではないでしょうか。世の中のひずみやゆがみを被告人の多くは背負っています。その人固有の問題、その人の人格だけに関わる問題だけではなくて。無罪を取ったからということではなく、その人たちが冤罪を掛けられることの苦しみのほうが大きい。また、たとえ有罪で罪を償っていても、被害者や社会は厳しい目でさげすむ。そんな方でも、命は愛おしいものであり、そのような状況でも、この世の中で生き抜くことはとても価値のあることです。弁護士の仕事として、一番大事なのは、その人たちに真剣に寄り添い、声を聞き、時には立ち直るきっかけになったり、被害者との関係も円満に進められるような関係を築くことではないかと思っています。
(「この弁護士に聞く第34回」『季刊刑事弁護』104号〔2020年〕を転載)
(2022年12月01日公開)