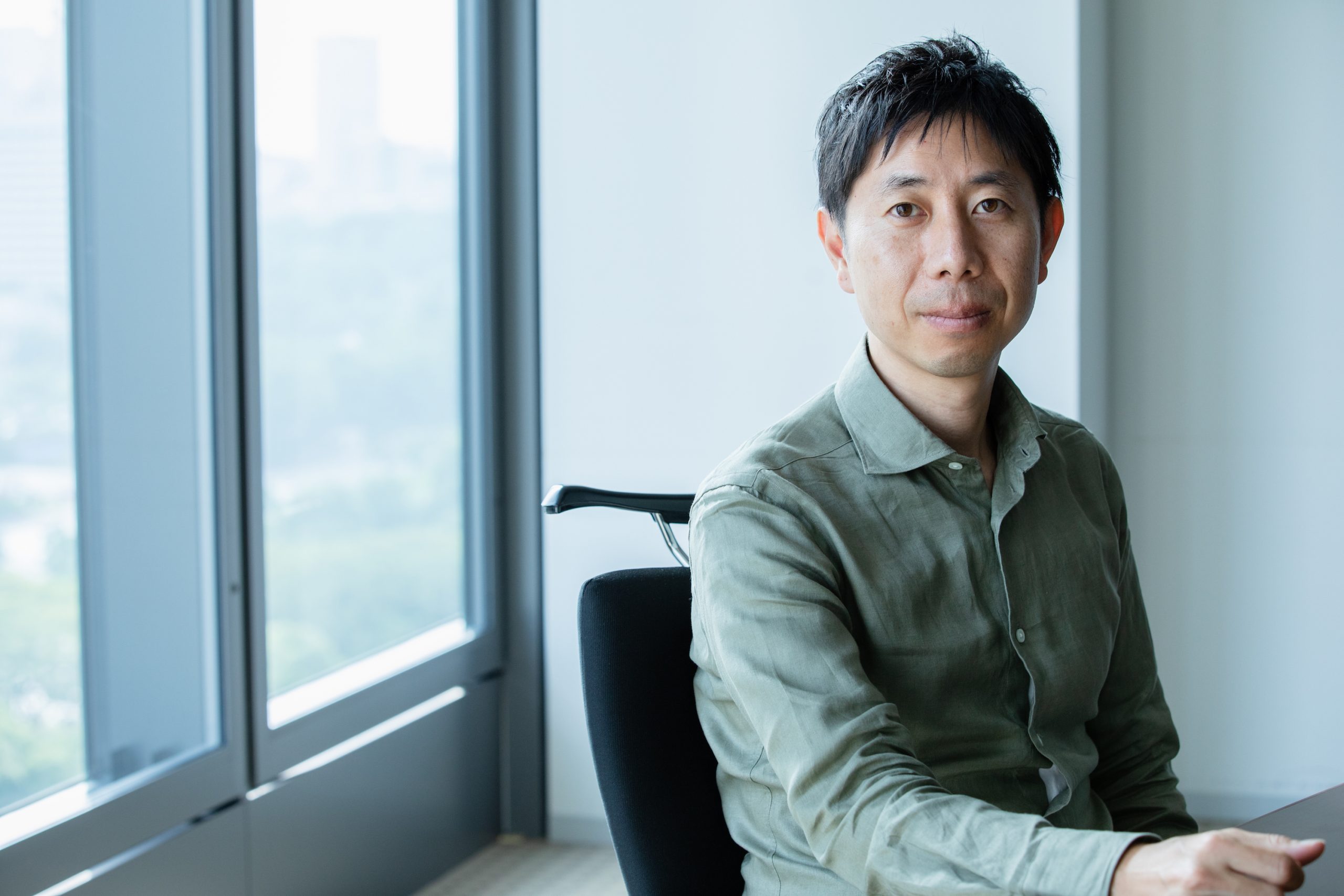2019年某日、谷口太規(たにぐち・もとき)は待ち合わせ場所にやってきた。2019年2月にCALL4を設立、代表を務める谷口は、現役の弁護士でありソーシャルワーカーだ。
その日はよく晴れた日だった。青空と鮮やかな緑が見渡せる窓際の椅子に向き合って座ると、そのまま静かに話は始まった。弁護士になったきっかけ、寝食も忘れて働いた日々、そしてアメリカ留学を機にCALL4を立ち上げるに至った経緯——。
終始、穏やかな語り口の奥に、“社会を良くする”ことに向き合い続ける熱量を感じて、私は背筋を伸ばした。ウエディング誌編集という訴訟とは関わりの薄い世界で仕事をしてきた私は、この時、ひょんなきっかけからCALL4の活動に参加したばかりだった。
CALL4はこの先、何を目指していくのか。今回のインタビューを通して、その絵を少しでもお伝えできたらと思う。
正義を見失い、葛藤し続けた日々
私はまず彼のルーツを知ることで、今の活動の軸が見えるのではと考え、なぜ弁護士になったのかを訊いた。
「学部時代は法学部ではなかったんです。社会学や哲学を専攻していました」
返ってきた答えは、意外なものだった。
「そして在学中は社会勉強と思い、お金を貯めて、バックパッカーにも行きました。それは今思い返しても、しんどい体験でしたね。
初日のバンコクで出会った人を信じて、資金50万円を全部騙し盗られてしまったんです。その後もかろうじて旅を続けながら、カンボジアに行けば少女買春に来ている日本人が沢山いて、でもそれにすり寄ってでも生きようとしている人たちがいる。荷物と自分を必死に守りながら、価値観はどんどんカオスになっていきました。『自分は愛だ、正義だと言ってきたけど、そういうものはもう分からないな』って」
約1年後、帰国。そして大学4年になった時、9.11が起きた。
「みんな凄く衝撃を受けているのだけれど、キャンパスで会っても『何も言えることはない』というように、誰もが無言だったのを今でも覚えています。
自分の価値観が揺らぐ日々の中で、アメリカによるアフガン侵攻が始まって、私は何かを求めてNGOなどの集会にいくつか足を運びました。その時、あるご老人が『今の若者たちは怒ることをしない』と言った。でも自分は、それはちょっと違うんじゃないかと思ったんです」
そこで、少し間を置き、言葉を選んだ。
「正確に言えば、『怒れないことと向き合い戦うことの方が、自分たちにとって重要なのでは』と思ったんです。当時の若者たちは結局、何が正しいのかが分からなくなって、それで内なるものの発露の途中で感情がしぼんでしまっているのでは、と感じて」

情報化社会では、世界のニュースはすぐ個人の手に入る。けれど情報には当然に偏りもあるし、事情は複雑に入り組んでいる。谷口と同世代の私は当時、9.11の映像に携帯で出合った瞬間をよく憶えている。「相応の知識も実体験も持たない私には、何も言えることがないな」とぼんやり思った。そこには恥ずかしさもあったように記憶している。
「正しさというものに関心を持った私は、皆が立ちすくんでいる一方で、熱心に社会活動をする若者もいると考えて、アクティビズムを卒論テーマに選びました。そして、文献研究だけではなく、多くのアクティビストの若者たちに個別インタビューをしたんです。彼らは見た目も言動も尖っていない、ふつうの人たち。けれど、社会を変えようと、身の回りから行動を起こしている。その彼らを動かしているものを知りたかった。
結果、話はさまざまでした。例えば渋谷でゴミ拾いをしていた集団に動機を聞いた時は、こう答えてくれました。『ゴミ拾おうとすると、しゃがむじゃないっすか。そこからの街の見え方がなんか違うんっすよ』って(笑)」
当時のフィールドワークの様子を思い浮かべ、思わず笑い合う。そして、谷口は言った。
「でも、そんな風にどうして一歩踏み出せるのかを彼らに聞き続ける中で、結論ではなく、人びとが話し合う“プロセスそのもの”が、とても大切なことだと気が付いたんです。
最終的な結論として『これが正しい』とは、なかなか指し示せないかもしれない。けれども、基本的に、人には力がある。だから人びとが話をしたり、聞かれたりできる場さえあれば、大丈夫なんじゃないか。むしろ、そのプロセスにこそ正義があるんじゃないか。
じゃあ自分は、その場を推進できる“代理人”になろう。そう思って、司法試験を受け、弁護士になりました」
“公共”、そして“公共訴訟”とは
ここで、谷口のこれまでの経歴を簡単にお伝えしたい。
2006年より弁護士活動を開始。年60件の刑事弁護を担当するなど多忙な日々の後、2015年、ミシガン大学ソーシャルワーク大学院に留学。卒業後は刑務所出所者の社会復帰支援に携わり、2018年帰国。現在は、東京パブリック法律事務所で共同代表を務める傍ら、公共訴訟支援プラットフォーム『CALL4』の活動に取り組んでいる。
「弁護士になった時、大きな社会課題に取り組む事務所と、名もなき人の名もなき事件を扱う事務所の二択で迷って、最後は関心を持っていた“パブリック”というフレーズの付いた後者を選んだんです、名前で」
谷口は笑った。しかし、現在の谷口にとっても変わらず、“公共(パブリック)”はキーフレーズなのだと思う。例えばCALL4では、国や行政を相手にした訴訟を、“公共訴訟”と呼んでいる。
谷口は、今でも忘れられないという、公共訴訟のエピソードを教えてくれた。
「弁護士のトレーニング期間に師事した先生は、岡山で行政を相手にハンセン病の訴訟をされていた方。当時、長島愛生園という、国の療養所に連れて行っていただきました。しんとしていて、とても静かな場所でした。なぜなら過去、ハンセン病の子供は同じ病気になる可能性があるからと強制堕胎させられていたため、そのコミュニティには全く若者や子供がいなかったからです」
そこで少し静寂があった。谷口は何かを思い返しているようで、私もその静けさについてを想像した。

「そのハンセン病訴訟では、原告のおじいさんやおばあさんたちが、訴訟を重ねるうちに、すごく変わっていったと言われているんです。
『自分たちみたいな人間が入っていいんでしょうか』と、最初は裁判所に入ることさえ躊躇されていた方がたが、裁判で自身のストーリーを初めて口にして、認知され、承認されていった。そこで『自分が受けた被害はこういうことなんだ』『こんな風に生きていいんだ』という気付きが生まれた。訴訟の場が、尊厳を回復していく過程になったのだと思います」
谷口は繰り返した。
「誰かが耳を傾けてくれ、公共に認知されることは大切です」
辞書を引けば、公共とは、社会一般。“私的な領域に対立する、公的な領域として、人間生活を成り立たせるもの”とある。そして、同じ社会に暮らす我々がありようを評価していくものだと。それであれば公共訴訟は、公共を問い、市民の手で新しい公共をつくっていく場でもあると言える。
しかし、日本の公共訴訟が置かれた環境は、決して良いものではないと言う。
「私が過去担当して敗訴したケースなのですが、ガーナからの難民の方が日本から強制退去を受けて、大勢に拘束されて飛行機に押し込められ、その場で亡くなった事件がありました。どう考えても拘束が引き金になっているのに、奇病による心臓発作で処理されてしまいました」
日本の公共訴訟は、諸外国に比べても、リソースが非常にアンバランスなのだ。
「こちらは、医師一人の意見を聞くだけでも、本当に大変。苦しい状況にある原告からのお金は見込めず、最後の頼りはポケットマネーです。そして一方の行政側は、どんどんお金を注ぎ込んで、専用スタッフも用意してくる」
思わず私は「そんな状況で、公正な場になるのですか」と訊いた。
「そう、だからこそ、CALL4の『4』。行政・司法・立法の三権に加え、社会を形作る四つめの力である、『市民』の出番なんです。国や行政は、誰も見ていないと分かって、やっているところがあります。場をもう少し市民に開くだけでも動きが変わるんじゃないか、という思いがあります」

穏やかな口調に怒りが滲んでいた。高い確率で原告側が敗訴するという公共訴訟。そこに向き合うには、原告や弁護団に果たしてどれだけの想いや労力が必要なのだろう。それはもはや犠牲といっても差し支えないのではないのか。
実際、世の中の変化や、司法制度改革で弁護士の数が増えたことによる平均給与の低下などから、それまで手弁当で賄われていた公共訴訟の次世代の担い手がいなくなってきているのだという。
「そこを仕組みから変えたくて、CALL4には訴訟のクラウドファンディング機能を最初から設けました」
(2021年08月27日) CALL4より転載