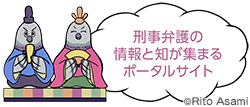5 自民党勉強会の「提言書」(つづき)
超党派議連の第1回実務者協議会が行われた翌日にあたる1月29日、自民党の国会議員有志で構成する「再審法に関する勉強会」(以下、「自民党勉強会」)が鈴木馨祐法務大臣に「提言書」を提出したことが報じられました。
突如登場したように見える「自民党勉強会」ですが、実はこの勉強会は、超党派議連が設立されるより前から存在していました。2023年春、再審法改正に向けた国会世論を盛り上げるため、与党自民党内に議論の場を設けようとした小林元治日弁連会長(当時)の呼びかけにより「非公開」の議論の場として設けられたものです。世耕弘成参議院幹事長(当時)を座長とする6名の自民党議員により同年6月から2024年3月まで合計6回の勉強会が開催されました。勉強会での議論には、法務省、最高裁、日弁連から数名ずつが参加し、主に法務省と日弁連が再審法改正をめぐる主要な論点について、それぞれの主張・反論を展開し、これを議員たちが聞いて、どのような法案がふさわしいかを検討する、という形で進められました。
ところが、2023年の暮れごろ、自民党旧安倍派の「裏金」問題が発覚、座長の世耕議員が「裏金議員」として世間の批判を浴びることになり、2024年4月には自民党を離党しました。「自民党勉強会」なのに、その座長が自民党を離れるという事態となったことで、勉強会は同年3月の第6回を最後に事実上休止状態となってしまいました(「提言書」によれば、その後も議員のみの議論を継続したとされていますが、その実情は不明です)。
1年近くが経過した2025年1月27日、勉強会サイドから日弁連に対し、「29日10時から勉強会を開催し、その日の夕方『提言書』を鈴木法務大臣に提出する運びとなった」旨の一方的な連絡がありました。自民党勉強会が突如「復活」したのです。
提言書では「高度の必要性を認めた事項」として、「同一事件に関与した裁判官の除斥・忌避」「再審請求審における証拠開示」「再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止」の3点について「立法について速やかに検討すべき」としています。ここまでであれば、議連の「骨子たたき台」とさほどの差異はありません。
しかし、よく読むと大きな違いがあります。一つは、再審請求審における証拠開示制度の対象を「通常審における類型証拠開示制度導入(平成16年改正)以前に確定した事件」に限定している点です。同手続の対象となる事件は刑事事件全体のわずか2.5パーセント程度に過ぎないことを日弁連が勉強会の議論で指摘していたにもかかわらず、このような縛りをかけているのです。これでは現行制度で裁判所の裁量により証拠開示が実現している再審事件のうち、類型証拠開示制度導入後に確定したものについては、法改正によりかえって開示を受けられない可能性すら出てきます。
何より問題なのは、提言書の最後に「今後の進め方」として、「再審制度について、社会的関心が高まっていることも踏まえ、運用上の措置等はもとより、法改正についても、刑事訴訟法を所管する法務省を中心に、速やかに着手すべきである」としている点です。超党派議連が議員立法による法改正に向けて実務者協議を始めた翌日に、「法務省を中心に」という提言を法務大臣に対して行う意図は、「議連ルート」へのけん制以外の何物でもないでしょう。休眠状態だった勉強会を法務省が利用し、このような発信をさせたのではないかとさえ思えるような動きでした。
6 正式に決定された法制審への諮問
自民党勉強会の提言書提出から約1週間後の2月7日、鈴木法務大臣が閣議後の記者会見で、再審制度について法制審に諮問することを正式に公表しました[1]。自民党勉強会の塩崎彰久議員は、自身のブログで「1月末に再審法改正に関する我々自民党7名の有志勉強会の提言を受け取って頂いてから、わずか1週間あまりでの迅速な対応」と、いかにも勉強会の提言が法務大臣の決断を促したかのように述べていますが[2]、法制審への諮問方針は、すでに昨年末から報じられていました[3]。法務省は昨年11月、「改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会」(本連載第18回参照)で、これまた唐突に再審制度について「論点整理」を行うとして10項目にわたる「論点整理案」を提示していましたが、11月22日(第16回)と2月5日(第17回)で論点整理を行ったとして、協議会での議論を終えました。議論の場を法制審に移行する準備が着々と進められていたのです。
来たる3月28日に法制審の臨時総会が開催され、「法制審議会再審制度部会」の設置が決まる見通しとなりました。超党派議連による議員立法をめざすルートと、法制審を経て閣法による改正をめざすルートが併存する事態が招来されようとしています。
7 「議連ルート」と「法制審ルート」の関係は
これまで、「刑訴法のような基本的法律の改正は、法制審での議論を経た法案を内閣が提出すべき」と言われてきました。しかし、閣法でなければならないと義務付ける法律はなく、むしろ議員立法を準備している国会の活動を行政府の諮問機関である法制審が抑制するのは行政による立法への介入であり、憲法に反するというべきです。
超党派議連は2月17日、鈴木法務大臣に要望書を提出しました。冒頭で「『えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟』は(中略)、再審法改正の先駆けとして総会での議論を重ねてきた。本年1月からは具体的な法案作成に着手し、今国会中に議員立法として法案を成立させたいと考えている」と宣言した上で、議連と法制審は対立するものではなく「切磋琢磨する関係」と位置づけました。その一方で、法務省がここまで消極的な姿勢であったことに対する国民の懸念を払しょくさせるためにも、法制審の委員として①冤罪被害者やその家族、②著名再審事件を支援し、再審制度の問題点を深く理解している弁護士、③過去に再審事件を担当した元裁判官を加えるべきと要望し、法制審の議論を公正中立な立場で進められる人選を強く求めました。
異例とも言える「ダブルトラック状態」に、当初法制審による再審法改正の見直しを歓迎ムードで報じていたメディアも、徐々に「国会の議論を優先すべき」という論調に変わりつつあります[4]。
前回紹介した超党派議連の「骨子たたき台」に盛り込まれた4項目は、すでに議論が尽くされ、立法事実も明らかなものばかりであり、これを一から法制審の議論に委ねるのはナンセンスです。まずは議員立法により、喫緊の最重要課題についての改正を今国会で実現させるべきでしょう。法制審がこの動きを止めることは許されません。
その上で、大正時代からほとんど変わらずに「老朽化」している再審法をオーバーホールするため、上記4項目以外の多岐にわたる論点を検討し、全面的な改正に繋げるのが法制審の役割というべきではないでしょうか。そうなると、超党派議連が要望したように、法制審のメンバーとしてふさわしい人選がなされるかどうかについても注視する必要があります。
ここでお手本を示してくれているのが台湾です。行政府が消極的な中、与野党の一致点に絞ってまず2015年の再審法改正を議員立法で実現させ、その後総統府直属の諮問会議での議論を経て2019年の全面改正を実現させました。この諮問会議のメンバーには冤罪被害当事者や再審弁護を経験した者も含まれていました。
議員立法による国会主導の再審法改正の実現を後押しするとともに、法制審を、これまでのような「法務省寄りの人選」による「時間稼ぎの場」としないための世論やマスコミの一層の発信が必要です。
8 忘れてはならない大事なこと
超党派議連が総会を開いて今国会への法案の上程を確認した2月26日、大崎事件第4次再審の特別抗告を棄却する最高裁の決定が弁護団に送達されました(決定は2月25日付)[5]。全部で23頁の決定文のうち、再審を認めない4人の裁判官の意見はたったの4頁で、判断の理由に具体的な証拠の引用もなかったのに対し、宇賀克也裁判官の反対意見は14頁にわたり、確定審のみならず累次の再審でも提出された証拠に言及しつつ詳細な理由を展開して「再審開始決定を行うべきである」と結んでいました。
大崎事件は3度にわたる再審開始の判断がされたにもかかわらず、検察官の不服申立てによって上級審で覆され、最初の再審開始決定から23年が経過しました。この6月で98歳になる原口アヤ子さんは、また振り出しに戻って第5次再審請求への準備を余儀なくされています。今回の宇賀裁判官の反対意見を含めると10人もの裁判官が有罪判決を見直すべきと判断したのに、です。
3月11日には狭山事件の石川一雄さんが亡くなりました。86歳でした。石川さんが申し立てていた第3次再審は2006年に申し立てられてから19年が経過し、ついに決定を見ることなく請求人の死亡によって終結しました。再審には受継の規定がないからです(本連載第9回参照)。
無実を訴える冤罪被害者が高齢化し、雪冤を果たせぬまま命尽きるという圧倒的な理不尽は、迅速な再審法改正によってしか解消されないことを、改めて肝に命じなければなりません。
【関連記事:連載「再審法改正へGO!」】
・第21回 動き出した二つのルート(上)
・第20回 最高検の「検証結果報告書」を検証する(下)
・第19回 最高検の「検証結果報告書」を検証する(上)
注/用語解説 [ + ]
(2025年03月24日公開)